USDT(テザー)とは?ステーブルコインの仕組み・特徴をわかりやすく解説
この記事を読み終わると得られること
- TetherUSDTについての基礎知識

▶ TetherUSDTとは?仮想通貨?
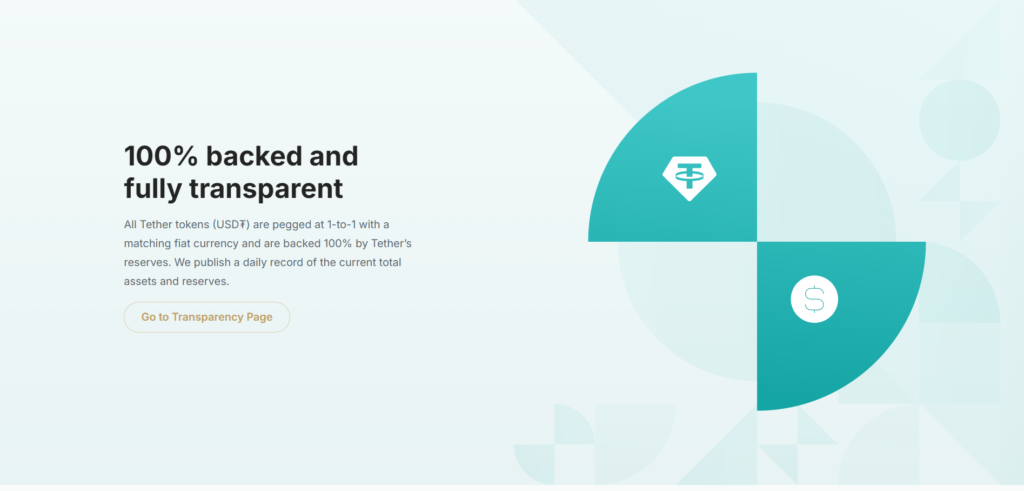
USDT(テザー)は、米ドルに価値が連動するステーブルコインです。”仮想通貨”ではないみたいです。
1 USDT = 1 USD を目安として価値が安定しており、暗号資産市場で法定通貨のように使われます。
ビットコインやイーサリアムのような価格変動が激しい暗号資産とは異なり、価格の安定性が特徴です。
▶ USDTとビットコインは何が違う?
1. 発行の仕組み
ビットコインは、サトシ・ナカモトによるホワイトペーパー “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”(2008年)に基づき設計されています。そこでは「二重支払いを防ぐための方法」として、Proof-of-Workに基づく分散型の合意形成が提案されました。
原文では次のように述べられています。
“To solve this, we proposed a peer-to-peer network using proof-of-work to record a public history of transactions that quickly becomes computationally impractical for an attacker to change if honest nodes control a majority of CPU power.”(p.3)
つまり、ビットコインは中央管理者なしで「計算資源=マイニング」によって新規発行され、最終的に2100万枚に上限が固定されています。
一方でUSDTは、テザー社という中央集権的な企業が発行主体となっています。新規発行は「準備資産(主に米ドル建ての現金や短期国債)」に裏付けされる仕組みであり、ブロックチェーン自体で分散的に供給が決定されることはありません。つまり、発行と価値維持のメカニズムが中央化されているのです。
2. どんな価値があるの?
ビットコインの価値は、Scarcity(希少性)とSecurity(安全性)に基づいています。ホワイトペーパーの設計思想の中でも「発行上限」と「改ざん不可能な取引履歴」が重要な要素です。
例えば、以下のように述べられています。
“Nodes vote with their CPU power, expressing their acceptance of valid blocks by working on extending them and rejecting invalid blocks…”(p.8)
これは、ビットコインの価値が「多数の誠実なノードによって検証される」点に依存していることを示しています。
対してUSDTの価値は「1USDT = 1USD」という裏付けです。テザー社が保有する資産に基づき、常に法定通貨と交換可能であることが信頼の根拠となります。したがって、分散的なマイニングやハッシュパワーではなく、発行者の信用・準備資産の健全性によって価値が維持される仕組みです。
3. ボラティリティの違い
ビットコインは市場原理に任せた変動資産です。ホワイトペーパーでは「価格」について直接は触れられていませんが、「信頼を前提としない電子取引システム」を目指したため、需給によって価格が大きく動きます。これが投資対象や投機資産としての魅力につながっています。
一方でUSDTは、ステーブルコインとして「価格変動を限りなくゼロに近づける」ことを目的としています。投資対象というよりは決済・送金・担保用途での利用がメインです。
4. 中央集権 vs 分散
この違いは、規制当局の介入や監査の必要性、取引所での扱われ方に大きな影響を与えています。
・ まとめ
ビットコインは「非中央集権」「発行上限」「Proof-of-Workによるセキュリティ」を備えたデジタル資産であり、USDTは「中央集権」「ドルとのペッグ」「価格安定性」を目的としたステーブルコインです。
両者は同じ「暗号資産」のカテゴリに含まれながらも、設計思想も役割も全く異なります。ビットコインは「デジタルゴールド」として長期保有の対象になりやすいのに対し、USDTは「取引や送金の潤滑油」としての役割を担うのです。
▶ USDTの仕組み
USDT(Tether)の仕組み(ホワイトペーパーなどより)
ホワイトペーパー:"Tether: Fiat currencies on the Bitcoin blockchain"
この文書でUSDTは次のように説明されています。
“At any given time the balance of fiat currency held in our reserves will be equal to (or greater than) the number of tethers in circulation.”
“Tether issuance or redemption will not face any pricing or liquidity constraints. Users can buy or sell as many tethers as they want, quickly, and with very low fees.”
つまり、USDTの設計上の核心部分は:
・ USDTの仕組み 詳細な構成要素
これをふまえて、USDTの仕組みを以下のように細かく整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行主体 | Tether Limited(中央企業)。USDTの発行と償還を管理。 |
| 裏付け資産(リザーブ) | 米ドルや米国債・短期債・キャッシュ等の流動性資産で裏付けられており、USDTの発行量を上回るか同等の資産を保有することが設計上の前提。 |
| 発行(Minting) | 利用者や取引所から法定通貨(USD等)を受け取った際に、新たにUSDTを発行する。発行数はその準備資産と一致またはそれ以下の範囲で維持される。 |
| 償還(Redeeming/Burn) | 保有者がUSDTをTetherに戻したい場合(または提携取引所などを通じて)、同等の法定通貨を受け取るような仕組み。USDTを “burn”(消滅させる)することで供給量が減る。 |
| 価格のペッグ(固定) | 通常「1 USDT = 1 USD」を維持することが目標。裏付け資産と償還性によってこの等価性が担保される。 |
| 透明性と監査 | ホワイトペーパーでは「Proof of Reserves(準備金証明)」を簡便だが効果的なアプローチとして導入。準備資産の報告・監査を通じて、USDT発行量との一致性を担保し、利用者の信頼を高めることが可能とされている。 |
・ USDTの利点と限界・リスク
仕組みを知ると、USDTには多くのメリットがある一方で注意すべき点も多数存在します。
・ ホワイトペーパーからの引用と解釈
ホワイトペーパーから直接の引用:
“Tethers exist on the Bitcoin blockchain rather than a less developed/tested ‘altcoin’ blockchain nor within closed-source software running on centralized, private databases.”
→ USDTは、よく検証されているビットコインチェーン(当初はOmniレイヤー)を利用することにより、信頼性と透明性をある程度確保しようとしている。
“Users can purchase tethers from Tether.to (our web-wallet) or from supported exchanges … Users can also transact and store tethers with any Omni Layer enabled wallet … Other exchanges, wallets, and merchants are encouraged to reach out to us about integrating tether …”
→ 発行・償還チャネルおよびUSDTの取引手段が広いことを意図しており、「利用者が自由にアクセスできる形で安定性を提供する」ことが設計指針の一つとなっている。
▶ USDTの将来性
・ 暗号資産市場での役割
USDTは、法定通貨と暗号資産をつなぐ「ブリッジ」の役割を持っています。
DeFiや取引所での決済・送金手段としての利用は今後も拡大すると見込まれます。
・ 規制・制度の動向
- 米国や日本でのステーブルコイン規制の影響を受ける可能性
- 透明性や担保保有のルール整備が進めば信頼性が向上
▶ USDTの入手方法と保管先の例
・ DEXなどでSwap(スワップ)して入手
①メタマスクマスクやBaseなどの仮想通貨ウォレットを作成、国内仮想通貨取引所からETH(イーサリアム)をウォレットに送金します。
関連記事:仮想通貨ウォレット公式リンク集
②DEXにウォレットを接続してイーサリアムメインネット上のイーサリアムからイーサリアムメインネット上のUSDTにスワップします。
関連記事:DEX公式リンク集

・ 【秘密鍵流出対策】LedgerやTrezorなどで保管
仮想通貨取引所などに入れず自身のコールドウォレットに入れる方法が、一番安全です。現状日本の仮想通貨取引所にはUSDTを預け入れられる場所がないため、メタマスクなどのホットウォレットやLedgerなどのコールドウォレットに入れるしかないです。
関連記事:LedgerとTrezorの対応通貨
▶ テザーUSDTまとめ
USDTは「米ドルに1対1で連動すること」を目的に設計された代表的なステーブルコインであり、その安定性によって暗号資産市場における基軸的な役割を担っています。価格変動の大きいビットコインやイーサリアムと異なり、投資そのもののリターンを狙う資産というよりも、資金を一時的に避難させたり、トレードの基準通貨として使う「安全地帯」としての性質が強いのが特徴です。
ただし、発行主体であるテザー社に依存している点、準備資産の内訳や透明性に課題が残る点は常に意識しておく必要があります。USDTは「分散型のビットコイン」とは正反対に、中央集権的な信頼構造に基づいているため、規制や監査、発行体の信用度が価値維持の根幹です。
事実、USDTとUSDC以外はよくデペグする印象があります。
USDTを使う上では「便利さ」と「リスク」の両面を理解し、必要に応じてコールドウォレットに保管したり、複数のステーブルコインを併用するなどリスク分散を意識することが重要です。USDTは投資対象というより、暗号資産市場での流動性・安定性を支えるインフラ的存在であり、ビットコインやイーサリアムとは全く異なる役割を持っているのです。
最後までお読みいただきありがとうございました。


